
|





|
建築基準法の改正により平成15年7月1日以降、居室の内装仕上げに使用する建築材料に共通の表示マークです。ホルムアルデヒドの発散等級に応じて、居室内への使用面積制限がありますが、F☆☆☆☆表示材料は無制限に使用できることになっています。
|
|
|



|
刺激臭のある無色のガス体です。水に良く溶け、35~37%の水溶液は通常「ホルマリン」と呼ばれて消毒や防腐剤として用いられています。合板、パーティクルボード、壁紙用接着剤等に用いられる尿素(ユリア)系、メラミン系、フェノール系等の合成樹脂や接着剤などの原料ともなるほか、一部ののり等の防腐剤や繊維の縮み防止加工等、さまざまな用途の材料として用いられています。
|
|
|



|
揮発性有機化合物(Volatile Organic Compounds)の略です。住宅室内の空気を汚染するVOCには、ホルムアルデヒドのほかにトルエンやキシレンなど様々なものがあります。現在、厚生労働省では、13種類の化学物質に室内濃度指針値を示しています。
|
|
|



|
Material Safety Data Sheetの略で、化学物質安全シートと呼ばれています。化学物質及びそれを含有する製品の成分や性質、取扱い方法などに関する情報が記載されています。平成13年度から実施された化学物質排出把握管理促進法では、政令で定める化学物質及びこれらを含む一定の要件を満たす製品について、平成13年1月からMSDSの提供が義務付けられました。
|
|
|



|
PRTR制度(環境汚染物質排出移動登録)とは、環境汚染の恐れのある化学物質の排出量、移動量のデータを事業所などが自治体に届け出をし、国がそれを公表するという、新しい化学物質管理の制度であり、ホルムアルデヒド、ダイオキシン、PCBなど354の物質が対象とされています。平成13年の春から施行されたこの制度は、行政、企業、市民が化学物質に関する情報を共有し、化学物質のリスク管理を適正に行うためのものとして注目されています。
|
|
|


|
シックハウスについて相談できる窓口にはどのようなところがありますか?
|
|
|


|
相談窓口としては次のようなところがあります。
(行政関係の窓口の例)
●国民生活センター ●保健所
●各地の消費者センター ●市役所などの環境衛生局
|
|
|


|
安心して工事を依頼できる施工業者にはどのようなところがありますか?
|
|
|


|
国土交通省の建築工事監理指針には施工業者の団体として、P12~13に掲載した(社)日本左官業組合連合会、(社)日本塗装工業会のほかに、日本外壁仕上業協同組合連合会及び全国マスチック事業協同組合連合会が紹介されています。
|
|
|



|
平成11年6月に成立した、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の通称です。住宅版PL法(Product Liability)、つまり住宅の製造物責任法とも言うべきものです。品確法は、「住宅性能表示制度」と「瑕疵担保期間の10年義務化」の2つの制度をもち、住宅の品質確保と消費者保護という大きな目的をもつ法律です。
|
|
|



|
構造耐力、遮音性、室内環境などの住宅の性能を表示して、住宅取得者が、事前に確認できるようにした制度です。新築住宅の性能を、住宅の工法・構造・施工者の別によらず共通に定められた方法を用いて客観的に示し、第三者(指定住宅性能評価機関)が評価することによって安心して住宅が取得できることを目的としています。
|
|
|



|
芳香族炭化水素系有機溶剤の代表格。無色透明で強い芳香があります。溶剤系塗料、接着剤、印刷インクなどの溶剤及び希釈剤として、通常は他の溶剤と混合して用いられています。
|
|
|



|
平成15年3月改正のJIS A6909建築用仕上塗材では、内装用の仕上塗材の品質に、ホルムアルデヒド規制対象外になるように原料規定が取り入れられ、品質に合格する仕上塗材にはF☆☆☆☆マークの表示をすることになりました。このため内装用の仕上塗材のJIS表示品は、居室への使用面積制限がなくなりました。
|
|
|



|
建築基準法の改正を受けて日本農林規格(JAS)が改正され、合板関係のホルムアルデヒド表示のFcoマーク等も、ホルムアルデヒド発散等級に応じて、第一種(無表示)、第二種(F☆☆)、第三種(F☆☆☆)、規制対象外(F☆☆☆☆)表示に変更されました。
|
|
|



|
環境にやさしい、環境保全に役立つ商品に表示されるマークのことです。(財)日本環境協会が平成元年から実施しています。
|
|
|



|
室内空気汚染にかかわるガイドラインとして、厚生労働省が定めている個別の揮発性有機化合物の室内濃度に関する指針値です。この指針値は「現状において入手可能な科学的知見に基づき、人がその化学物質の示された濃度以下の暴露を一生涯受けたとしても、健康への有害な影響をうけないであろうとの判断により設定された値」です。特殊な事情がある場合には、指針値以下であっても何らかの影響を受ける可能性があります。
|
|
|
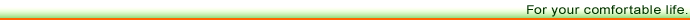


|
